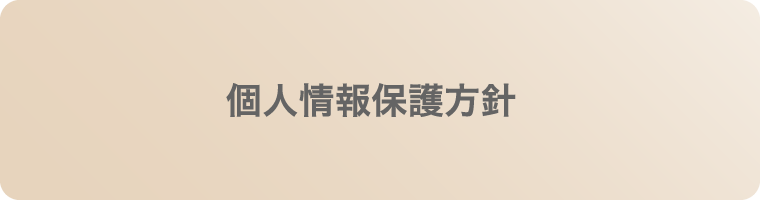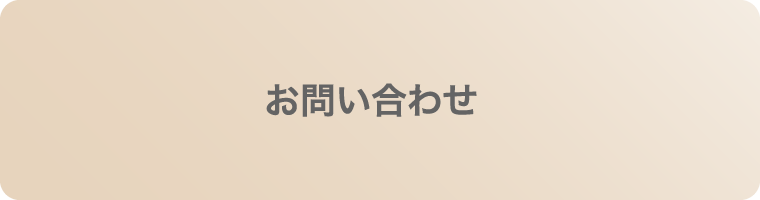ROomBOT: 自助的な生活動作支援に向けた空間知能化ロボティクス

慶應義塾大学大学院メディアデザイン研究科 Embodied Media Project
太田雅啓、吉田 貴寿、佐々木 智也、新居 英明、森田 迅亮
| 採択技術名 | ROomBOT: 自助的な生活動作支援に向けた空間知能化ロボティクス |
|---|---|
| 採択者名 | 慶應義塾大学大学院メディアデザイン研究科 Embodied Media Project |
| 採択年 | 2025年 |
※掲載している情報は、受賞当時の情報のため、現在は異なる場合があります。
詳細
高齢化社会が進行する中で、日常生活動作に不安を抱える人々が増えている。こうした人々は身体動作を行う上で他者の直接的な支援を必要としているが、医療・介護業界での人手不足は深刻な社会課題となっている。今後、ますます高齢化社会が進行する中で、他者の手によらない自立的な生活動作支援を行うための技術ニーズは高まっている。
本提案では、このニーズに対し、「空間そのものが支援ロボットとしてユーザーをアシストする」という新たな視点からアプローチし、自立を支える新しい生活空間のあり方を提示する。ロボットを単なる道具ではなく、人の身体の延長として空間に溶け込ませるアプローチにより、ROomBOTは、部屋スケールで稼働するロボットハンドをユーザーの意図に応じて操作可能な、空間統合型ロボット基盤である。天井に取り付けたケーブル駆動モーターにより、空間内を自在に移動できるロボットハンドを実現し、ユーザーの「もう一つの手」として機能する。本技術の大きな特徴は、ユーザーが自ら身体を移動させることなく、ベッド上からでも空間内の物体操作が可能になる点にある。たとえば水を飲む、リモコンを取るなどの基本的な動作が、他人に頼むのではなく自力で行えるようになると期待される。
ROomBOTは、ユーザーの意図に即した直感的な操作を可能にし、身体的負担をかけることなく高い自由度で行動を補助する。本技術は、身体的制約や空間的制約を超えて、人の身体能力を拡張するための新たなインフラとしての可能性を有している。これは、たとえば身体に不自由を抱えるユーザーでも他者に頼らず、自らの意思で行動できる環境の実現に貢献できる可能性がある。
社会実装
について
ROomBOTは、身体的制約を抱える人々が、自分の「もう一つの手」を得ることで生活の質を大きく向上させるロボットシステムである。社会実装においてはまず、在宅介護や療養施設への導入を視野に入れている。特に、寝たきりの高齢者や、四肢に障害を抱えるユーザーが自らベッド上でROomBOTを操作することで、基本的な日常動作を自力で行うことができるようになると考えられる。操作は視線やジェスチャーなど多様な方式に対応可能で、ユーザーの身体能力に応じた柔軟なUI設計が可能である。将来的には、AIによる意図推定やセンサ連携により、よりスムーズかつ直感的な操作体験を目指す。さらにROomBOTは、介護分野にとどまらず、遠隔地からの操作によるテレプレゼンスや簡易的なリモート作業支援など、幅広い応用可能性を持つ。
審査講評

高齢者や要介護者の部屋というのは、ヒトと見紛うヒューマノイドロボットや超ハイテクなマイクロファクトリー(高度に自動化された小さな工場)のようなものを連想しがちだが、少なくとも当面は、こんなちょっと不格好なものにしかなりえないのではないか。価格や利用者の心理からくる市場適合性というものがある。誰も答えを出していない領域なので試行錯誤する価値がある。家や部屋がロボットになる例で、印象に残っているのは米国Syfyチャンネルで放送された『ユーリカ』というドラマだ。興味深かったのは、家が主人公を飲み込んでいる形になるので、独占欲のような感情をもち主人公の生活に介入しはじめるあたりだった。コンテンツ性も重要である。
(遠藤諭 委員長/株式会社角川アスキー総合研究所 主席研究員/MITテクノロジーレビュー日本版 アドバイザー/ASCII STARTUPエグゼクティブ・アドバイザー)